「事業計画」と「企業分析」は経営の両輪としての活動
Biz/Zine編集部・栗原茂(以下、栗原):お二人が互いのご著書をどのように読まれたかお聞かせください。木村さんから見た、村上さんの『決算分析の地図 財務3表だけではつかめないビジネスモデルを視る技術』(ソシム)の特徴は何だと思われますか。
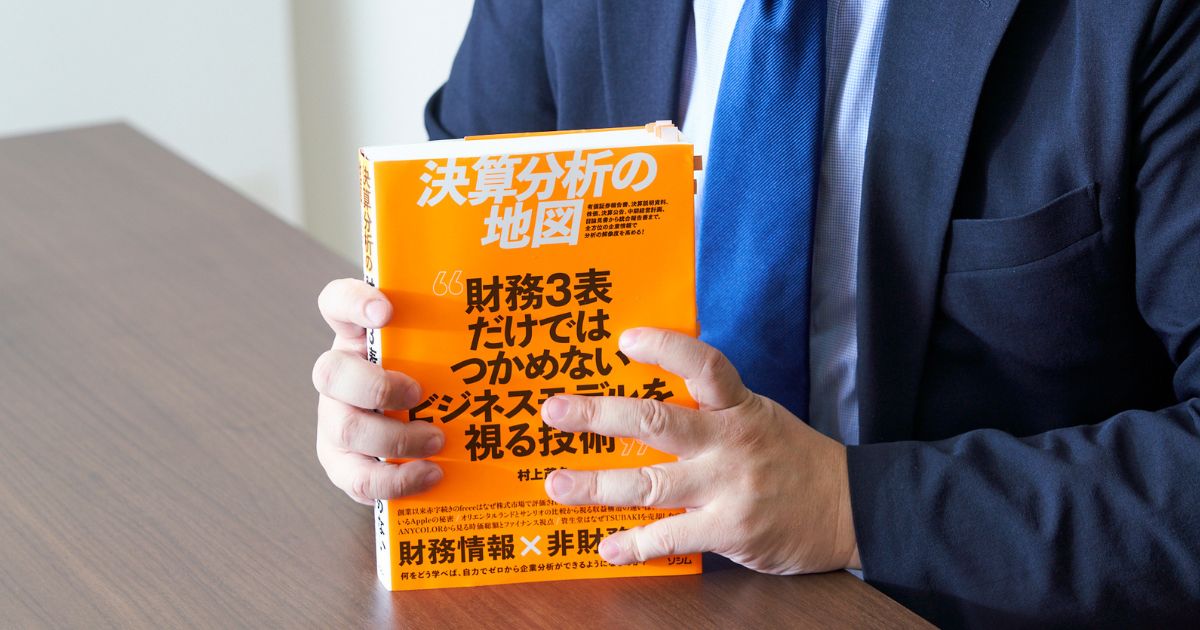
木村義弘氏(以下、木村):決算分析に関する本は数多くありますが、村上さんの著書は、物事を非常に構造的に説明されている点が素晴らしいと感じました。「こういう風に伝えればよかったのか」という発見の連続でした。
たとえば、多くの人がつまずきがちな「ROE(自己資本利益率)」の説明1つとっても、株主からの「インプット(純資産)」と株主への「アウトプット(当期純利益)」で捉えるという考え方は、本質的な理解を格段に進めます。

一度きちんと概念を抽象化し、それをオリエンタルランドからAirbnbまで多岐にわたる具体的な企業事例に落とし込んでいるので、企業分析の本質が滲み出ています。単なる指標の羅列ではなく、その意味をご自身の中で完全に消化されているからこそ書ける内容で、決算分析を学ぶ最初の一冊として非常におすすめです。
栗原:村上さんは『決算分析の地図』を執筆される際、どのような読者を想定されていましたか。また、本書の骨格である「7つの定石」はどのように生まれたのでしょうか。
村上茂久氏(以下、村上):実は、元々のターゲットは会計初心者から一歩進んだ、中級者以上を想定していました。初心者向けにはすでに質の高い名著がたくさんあります。だからこそ、もう少し専門的でありながら、学術的で難解になりすぎず、実例が豊富な本が少ないと感じ、その領域を狙いました。
本書の骨格である「7つの定石」は、全てを書き終えた後に、最後に追加したものなんです。当初は、決算短信や有価証券報告書等のさまざまな企業に関する情報を網羅した「地図」を作るコンセプトだったのですが、書き上げたものを読み返したときに、何か物足りなさが残りました。研修でよく「話は分かったけれど、いざ自分で分析しようとすると何から手をつけていいか分からない」という声を聞いていたことを思い出し、読者が自分で実践できるためのフレームワークが必要だと考えたのです。

そこで、私自身が無意識に行っていた分析プロセスを棚卸しして7つのステップに落とし込み、書き上げた本文に後からそのフレームワークを当てはめて再構成しました。これにより、読者が思考のプロセスを追体験し、自ら分析を実践できるようになることを目指しました。
「リーディング」と「ライティング」。ファイナンス思考を支える2つの技術
栗原:では逆に、村上さんから見た木村さんの『事業計画の極意 仮説と検証で描く成長ストーリー』(中央経済社)の特徴をお聞かせください。
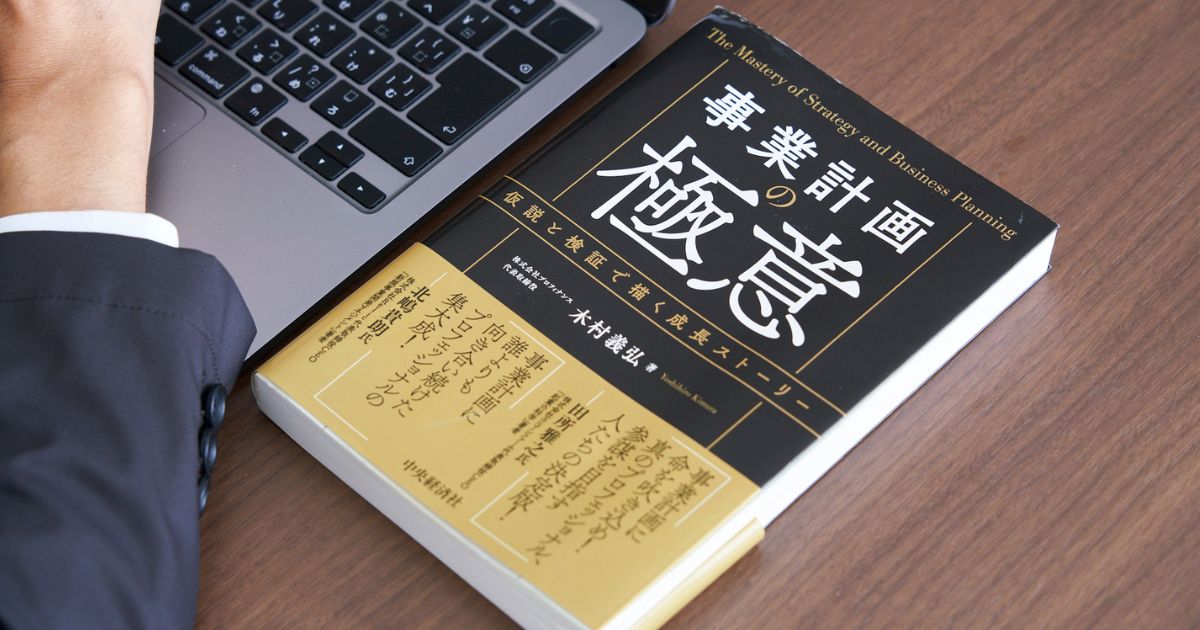
村上:ポイントは2つあります。1点目は、事業計画というテーマにおいて、これまで誰もが手探りだった領域に、明確な指針を示してくれたことです。コンセプトとしてどう計画を立て、それを客数や客単価といった具体的なKPIにどう分解していくか。その実務的なプロセスが、手に取るように分かる形で書かれています。経験者にとっても「暗黙知」が「形式知」に整理されていて発見が多く、初心者にとっては、まず何から始めればいいかの全体像を示してくれる羅針盤のような本です。
2点目は、脚注や引用が非常に充実しており、専門書としての知的な深みがある点です。アイゼンハワーの言葉が引用されるなど、理系的なロジックをベースにしつつも、文学的なエッセンスが散りばめられていて、読み物としても非常に面白いですね。























